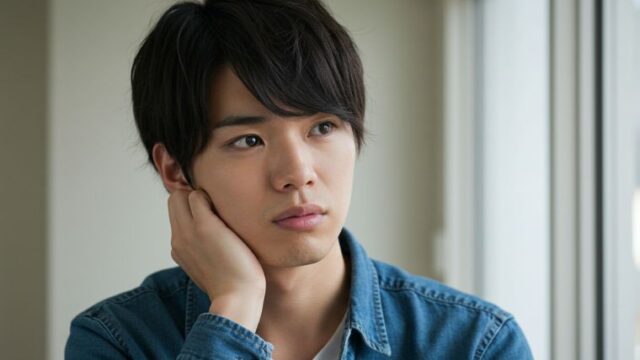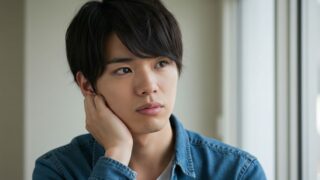「彼女がいつまでたっても敬語をやめない…これって普通なの?」
こんな悩みを抱えている人、意外と多いんです。
付き合って半年、いや1年…それでも彼女がずっと敬語。
たまにタメ口になるのかと思いきや、会話は終始「です・ます調」。
最初は「なんか礼儀正しくていいな」なんて思っていたけれど、だんだんと距離を感じるようになってきた…そんなことはありませんか?
実際、「彼女が敬語をやめない」という悩みはネット上でもよく見かけます。
しかも、年下彼女×年上彼氏のカップルに多い傾向があるようです。
「もしかして、俺のこと本当は好きじゃない…?」なんて不安になることも。
でも、焦らなくて大丈夫。
実は、彼女が敬語を続けるのにはちゃんとした理由があるんです。
この記事では、
を紹介していきます。
彼女との距離を縮めるヒント、見つかるかもしれませんよ。
さあ、彼女の気持ちをちょっとだけのぞいてみましょう。
記事の目次
彼女が敬語をやめない理由とは?心理と環境の影響

「付き合ってもう半年…なのに、彼女がいまだに敬語。なんで?」
敬語を使われ続けると、「俺ってまだ距離を置かれてる?」と不安になることも。
でも、彼女が敬語をやめないのにはちゃんと理由があります。
目上の人と接することが多い環境にいる
彼女が会社や学校で目上の人と接する機会が多いと、敬語が習慣化してしまっている可能性があります。
特に、上司や先輩とのやりとりが日常的な環境では、プライベートに切り替えるのが難しくなることも。
「恋人と話すときはタメ口!」とスイッチを入れられればいいですが、一度染みついた敬語はなかなか抜けません。
敬語のほうが落ち着く、安心する
これ、意外と多いんです。
「タメ口より敬語のほうがしっくりくる」
「敬語で話しているほうが、落ち着いて話せる」
彼女にとって敬語が “安心できるコミュニケーション” になっている場合、無理にタメ口にするほうがストレスになってしまうこともあります。
恥ずかしさや「今さら感」がある
「タメ口にしたいけど、今さら切り替えるのが恥ずかしい…」
こんな心理も働いているかもしれません。
付き合い始めに敬語を使っていた場合、それが続くと「急にタメ口にしたら変かな?」と気になってしまうことも。
特に、彼氏が年上の場合、「いきなりタメ口にしたら失礼かな?」と考える女性も多いです。
彼氏を尊敬している、立てたい気持ちがある
「敬語を使う=まだ心を開いていない」というわけではありません。
むしろ、「彼氏のことを尊敬しているからこそ、敬語を使ってしまう」ケースもあります。
「好きな人の前では、丁寧な言葉を使いたい」という心理ですね。
とはいえ、「ずっと敬語だと寂しい」と感じる人もいるはず。
では、どうやって自然にタメ口に移行すればいいのか?
それは、次で詳しく解説していきます。
彼女に自然にタメ口になってもらう方法5選

彼女に「タメ口にしてほしい」と思っても、急に「敬語やめて」と言うのは少し気まずいですよね。
無理に敬語をやめさせるのではなく、自然にタメ口に移行する方法を試してみましょう。
まずは自分からフランクな話し方に変える
敬語が習慣化している彼女は、あなたが敬語を使っていると、つられて敬語を続ける可能性が高いです。
そこで、まずは自分からタメ口を意識的に増やすことが大切。
フランクな口調で接すれば、彼女も自然と影響を受けてタメ口になりやすくなります。
名前やあだ名で呼んでもらうようお願いする
彼女が敬語を使い続ける場合、多くは「苗字+さん付け」で呼んでいませんか?
これは、言葉遣いだけでなく、心理的な距離がまだあるサインです。
「◯◯(下の名前)って呼んでみて」と軽くお願いしてみるのもアリ。
名前を呼び捨てにすると、敬語が抜けやすくなるという心理的な効果もあります。
LINEやスキンシップのときにタメ口を促す
LINEではタメ口なのに、会話では敬語という彼女も多いですよね。
この場合、LINEでの口調をヒントにして、実際の会話でもタメ口を促すことができます。
例えば、LINEで「ねえ、今日会ったときもその口調で話してよ(笑)」と軽く伝えてみるのも効果的。
また、手をつないだり、近い距離で話しているときに「今だけタメ口ね!」とお願いするのもアリ。
罰ゲーム方式を取り入れてみる
ちょっと遊び感覚で、「1回敬語を使ったら罰ゲームね!」と軽くゲーム感覚で楽しむのもアリ。
真剣にお願いすると気まずくなることもあるので、楽しい雰囲気の中でタメ口を促すのがコツです。
例えば、「敬語を言ったら〇〇する(変顔する、ジュースを奢る)」など、軽いルールを決めてやってみるのもアリ。
楽しくタメ口に移行できるかもしれません。
彼女がタメ口を使ったときにリアクションする
タメ口が出たときに、「おっ、タメ口になってる!嬉しいな!」とリアクションすると、彼女も「タメ口にしてもいいんだ」と安心します。
逆に、「お、珍しいね(笑)」みたいに突っ込んでしまうと、「やっぱり違和感があるのかな…」と不安にさせてしまうことも。
タメ口をポジティブに受け入れる姿勢を見せるのが大切です。
タメ口への移行は、彼女の性格や環境によってスムーズにいかないこともあります。
でも、無理に変えさせようとせず、自然な流れでタメ口を使いやすい雰囲気を作ることがポイントです。
敬語を続けるメリットとデメリットとは?無理にやめさせるべき?
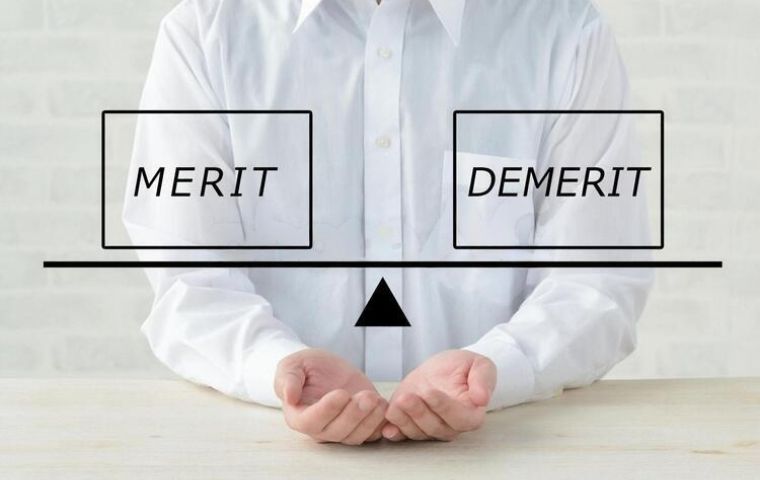
「彼女が敬語をやめない=関係がうまくいっていない」 というわけではありません。
実際、敬語を続けることで得られるメリットもあるんです。
逆に、デメリットもありますよね。
ここでは敬語を続けることで生まれる影響を整理してみます。
敬語を続けるメリット
敬語を続けることで、彼女は「大人っぽく見られる」「礼儀正しい女性に見える」といったメリットを感じているかもしれません。
また、敬語を使っているとケンカになりにくいという意見もあります。
タメ口だと感情的になりやすいですが、敬語が入ることで言葉遣いが丁寧になり、冷静に話せるケースも。
敬語を続けるデメリット
敬語が続くと、やはり「よそよそしい」「壁を感じる」と思う人も多いです。
特に、付き合いが長くなっても敬語のままだと、「彼女は本当に心を開いているのかな?」と不安に思うことも。
また、敬語だと遠慮が出てしまい、お互いに本音を伝えにくくなる場合もあります。
無理にやめさせるべき?
結論から言うと…無理にやめさせる必要はありません。
敬語にはメリットもありますし、彼女が安心して話せるなら、それはそれで良いこと。
ただ、「敬語だと寂しい」と感じるなら、その気持ちは伝えてもいいでしょう。
「敬語が嫌というわけじゃないけど、もう少しフランクに話してくれたら嬉しいな」と、彼女がプレッシャーを感じない形で伝えることがポイントです。
彼女が急に敬語になった…これって何かのサイン?理由と対処法

「今までタメ口で話していたのに、急に敬語になった…」
これ、意外と焦りますよね。「え、なんか怒らせた?」とか「気持ちが冷めたのかな?」と不安になってしまうもの。
でも、突然の敬語にはいくつかのパターンがあるんです。
気持ちが冷めてしまった可能性
これは正直、一番心配なパターン。
彼女があなたに対しての気持ちが変わってしまった場合、無意識に距離を置くために敬語を使うことがあります。
こんな変化があれば、ちょっと注意が必要。
彼女の態度をしっかり観察しながら、一度冷静に話をしてみるのも大切です。
何かしらの不満や怒りを感じている
「さっきまで普通だったのに、急に敬語になった…」という場合、あなたに対して怒りや不満を感じている可能性もあります。
こんな場面では、彼女はあえて敬語を使うことで「ちょっと怒ってますよ?」と遠回しに伝えようとしているのかもしれません。
「何か気になることある?」と優しく聞いてみると、彼女の本音が出てくることもあります。
気を引き締めたい・距離を保ちたいと思っている
意外と多いのが、「なんとなく敬語に戻してみた」というケース。
例えば、「少し冷静になりたい」「いつもより距離感を意識したい」と思ったときに、無意識に敬語に戻ることがあるんです。
この場合、無理に理由を聞き出そうとせず、彼女のペースに合わせるのがベスト。
「最近、ちょっと距離を感じるんだけど、大丈夫?」と優しく聞いてみると、本音が聞けるかもしれません。
ふざけて敬語を使っているだけ
「敬語になった=悪いサイン」と決めつけるのはまだ早いです。
中には「ふざけて敬語を使っているだけ」という場合も。
冗談っぽく「〇〇さん、今日も素敵ですね~!」なんて言ってくること、ありませんか?
こんな場合は「あえてふざけているだけ」なので、特に気にする必要なし。
彼女が急に敬語になったら焦らず冷静に対応しよう
彼女の敬語が急に復活したとき、大切なのは何が原因なのかを冷静に見極めることです。
- 最近の彼女の態度をよく観察する
- ケンカや不満がないか思い返してみる
- 落ち着いて「何かあった?」と聞いてみる
いきなり「なんで敬語なの!?距離感じるんだけど!」と責めるのはNG。
彼女の気持ちを尊重しつつ、ゆっくりと話をしてみることが大切です。
まとめ:彼女に敬語をやめさせるべき?
彼女が敬語をやめない理由には、環境・心理・習慣など様々な要因があります。
無理にタメ口にさせる必要はありませんが、「敬語だと距離を感じて寂しい」と思うなら、その気持ちは伝えてOK。
大事なのは、プレッシャーをかけずに自然な形で変えていくことです。
- まずは自分がフランクに話す
- 名前やあだ名で呼んでもらう
- 軽いノリでタメ口を促してみる
敬語かタメ口かよりもお互いが心を開いて話せることが何より大切です。
言葉遣いより、関係の深さを意識していきましょう!